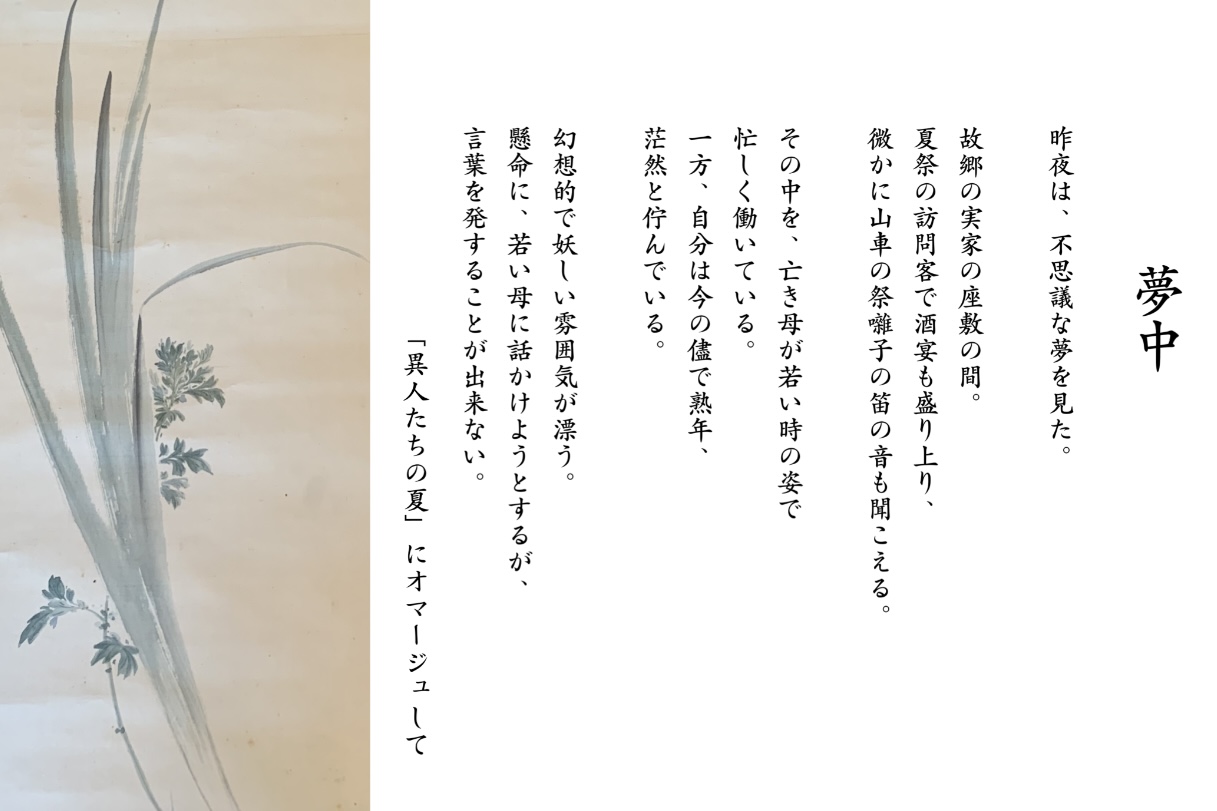《写真漢詩》祭囃子が聞こえると、、、(後編)
突然だが、「異人たちとの夏」の話だ。「岸辺のアルバム」や「ふぞろいの林檎たち」の山田太一の原作を、市川森一が脚本化し、大林宣彦がメガホンを取った1988年の松竹映画だ。
「大林流家族映画」と言われ、「不自然な設定」にも関わらず、観客は自然にその世界に引きこまれていく。私の大好きな映画だ。ストーリーはネタバレになるから詳しくは書かないが、私が強く惹かれる「不自然な設定」とはこんな感じだ。「主人公の人気シナリオライター(風間杜夫)が、ふとしたキッカケで、自分が12歳のときに交通事故で死んだ両親(片岡鶴太郎&秋吉久美子)と出逢い、ひと夏を過ごす。」「両親は当時のまま若く、自分は現在の年齢、従って大人同士で話も弾み楽しいときを過ごすが、主人公は両親との逢瀬を重ねるごとに痩せて衰弱していく、、、」
実は、私もそんな経験がある。と言っても私のは夢の中での経験だ。私はその夢を毎年この時期になると見る。夢の設定は常に故郷の祭り(前編参照・リンク)の夜だ。実家の座敷を俯瞰しているシーンから始まる。「異人たちとの夏」と同じように両親は若い。父は座敷で祭りに招待した会社の同僚たちと酒宴で盛り上がっている。母は訪問客たちの料理を運ぶのに忙しそうだ。
唯、気が付けば、当時なら近くで遊んでいるはずの幼い私の姿が無い。一方で、父母を見ている私はと言えば、どう見てもその時の父母よりもずっと歳を取っている。不思議だなと思って、母に聞こうと声を掛けようとするが、、、声が出ない、、、必死で声を出そうとするが、どうしても声は出ない。そして母も気付こうとしない、、、いつも夢はそこで終わってしまう。
「異人たちとの夏」の「異人」とは、既に亡くなってもうこの世には存在しないはずの人だ。最近、私は気付いた。私の夢の中で、両親に声を掛けようとしても、私の声が出ないのには理由があると。
私の両親も「異人」ではあるが、「異人たちとの夏」の両親とは違い、絶対に嫌だったのだ。ひょっとして万が一にも私の声が出て、「異人」の両親と私が話すことになるのが、、、結果、私が衰えていくことが、、、両親が、私が「異人たちとの夏」の世界に入っていくことを阻止してくれているのだと。
祭りの夜に聞く祭囃子は、昼に聞くそれとは違い少し寂しげだ。私には時に妖しげに聞こえることもある。笛の音に釣られ、亡き父母の若い頃を思い出すこともある。酒の酔いに釣られ、夢と現の間を彷徨う心地になることもある。危ない危ない。そんな時だ。「異人たちとの夏」の世界からの招待状が届くのは、、、今年もまたそんな季節になった。