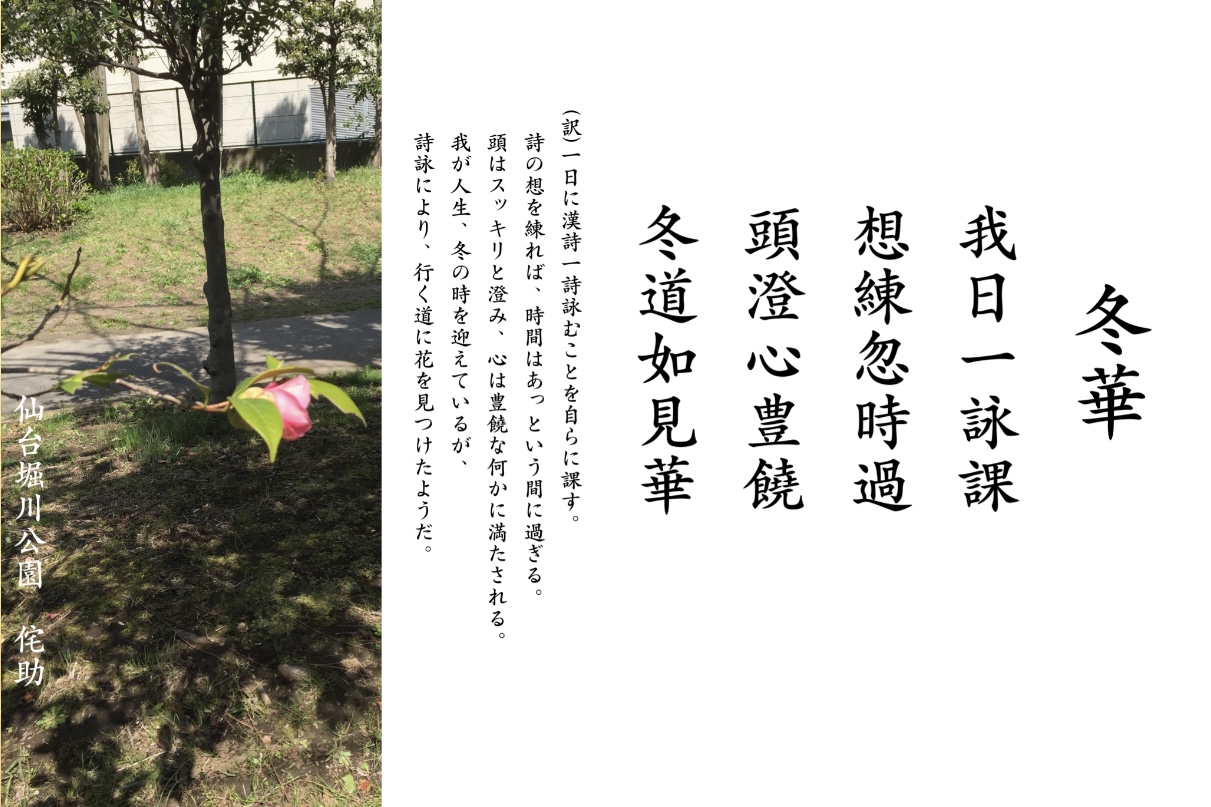《写真短歌》四長、インスタ映えの中で富山独立の歴史を考える(富山吟行3・富山市ガラス美術館)。
『富山市ガラス美術館』である。外観は隈研吾設計、同じ建物にこれもお洒落な富山市立図書館が入る人気のインスタ映えスポットである。
 |
| 隈研吾設計の外観 |
富山市ガラス美術館、名前に「立」が入っていないが公立美術館である(これもお洒落!)。富山とガラス!不勉強の私はその繋がりがよく分からなかったが、地元の人に聞いて成程!と納得した。そこには富山の重要歴史の一つが隠されている。富山人の独立精神形成の物語だ。(何処からの独立か?それは金沢、加賀藩からの独立だ。幕藩体制の江戸時代、藩は国そのものだった。)
富山のガラス産業、始まりは江戸・明治期の「富山の売薬(越中富山の薬売り)」の「薬瓶」製造だ。当時、薬の効き目は勿論だが、「薬瓶」の出来は重要だった。高価な瓶から出てくる丸薬はいかにも病気に効きそうだ。それを見ただけで治る病気もあったのでは、、、一種のフラボノ効果だ。当然、富山の製薬商・売薬商は「薬瓶」のためのガラス技術研究・製造に多くの資本を投じることになった。
そして時代はさらに遡る、ではそもそもの富山に於ける製薬産業興隆のキッカケは、、、それは1963年、富山藩の加賀藩からの分藩、即ち独立だ。分藩したものの富山藩は、参勤交代や幕府から命じられる手伝い普請などで財政難に苦しめられる。しかし、そこで本藩の加賀藩に援助を求めれば、藩の運営に干渉され独立が脅かされる、、、
その打開策として富山藩が目をつけたのが、室町時代から萌芽はあった地元の製薬産業だ。2代富山藩主前田正甫に至っては、自ら合薬を研究し、有名な「富山反魂丹」を開発、自ら江戸城で宣伝(江戸城腹痛事件など逸話も残る)に努め、富山の薬を全国ブランドにした、、、
そんなことを、頭の中で復習しながら、『富山市ガラス美術館』に入場すると、また別な趣きが、、、てなことは全く無い!
そこは完全に映えの世界!富山の現代ガラス作家たちの織りなすイリュージョンの世界だ!圧倒され、「薬瓶」のことなどすっかり忘れた。